浄化槽保守点検記録票の検査、点検項目について
|
*当社で保守点検のご契約をされているお客様には、必ず浄化槽保守点検記録票をお渡ししております。そちらをごらんの上、参考になさってください。 2009年4月より順次新浄化槽保守点検記録票を導入いたしました。従前はわかりにくい、 見づらい、との声をいただいておりましたので、新年度より順次切り替わっております。 |
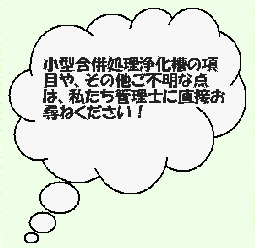 *は、浄化槽の処理方法や立地によっては、点検項目に斜線が引かれている場合があります。
*は、浄化槽の処理方法や立地によっては、点検項目に斜線が引かれている場合があります。
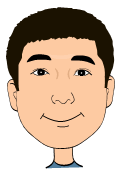
保守点検作業
|
点検項目 |
説明 |
|
消毒槽pH |
浄化槽の処理段階でいえば、最終のところが消毒槽です。そこのpHを計ります。中性(7)前後であれば、浄化槽内に住む微生物にとってそこは最適な環境と考えられます。 |
|
消毒槽残留塩素 |
処理の最終段階で、塩素により大腸菌群を消毒し3000個/ml以下にするようにしています。放流水中に含まれる残留塩素を測ることにより確実に消毒されていることが確認できます。同時に、放流水域に生息する生態系に影響を与えていないか、薬剤の使用が適切かどうかもみています。 |
|
消毒槽透視度 |
水中のSS(Suspended Solids、浮遊して濁っている1μm〜2mmほどの小さい物質)が多ければ透視度が下がり、水質の改善が必要と判断されます。 |
|
消毒槽亜硝酸反応 |
GR試薬を使い、採水した水が赤く変化するかどうかを調べます。 |
|
バッキ槽DO*・水温 |
DOは、溶存酸素を指します。好気性処理槽(バッキ槽)では、酸素が少ないと微生物が死んでしまいます。また、多すぎても微生物が増えすぎてしまうことになり、結果的には酸素の供給が追いつかなくなるため、死んでしまいます。DOが最適な状態になっているかどうか確認、調整する必要があります。DOと同様に、水温も微生物にとって住みやすい状態に保たれているか測ります。水温が高いとDOが低くなるので、この2つは密接に関係しています。 |
|
SV(10)* |
Sludge Volumeの略です。汚泥沈殿率ともいいます。通常は、汚泥をメスシリンダーに取り、30分後の様子をみますが、家庭用の浄化槽保守点検では、便宜上10分後の様子を見ます。これにより、擬似的に浄化槽内のようすを再現し、内部の汚泥がどのような状態にあるかがわかります。 パーセンテージが少なすぎると浄化のための汚泥(微生物)が少なく、多すぎると内部が汚れている(清掃しないと微生物が流出してしまう状態)、と判断できます。 |
|
流入管渠(かんきょ) |
トイレやお風呂場、台所と浄化槽とを結ぶ管に、詰まり、亀裂や破損があると漏水や滞水の原因になります。滞水は、害虫発生やにおいの元にもなります。 |
|
流入口 |
浄化槽内部はいくつかの処理室に分かれています。流入管渠をとおってきた汚水はまず沈殿分離室へ。トイレクイッ○ルや異物を一度に流すとまずここで詰まってしまうトラブルの多い部分です。異物は保守点検時には取り除いています。 |
|
スカム・汚泥量 |
処理室のひとつである沈殿分離室のスカムや汚泥がどのくらいかをみます。通常の使用でスカムは存在しますが、限界値を超えて放置していると、導入管が詰まったり、トイレの流れが悪くなったり、大雨の時には流出・においの発生にもつながります。汚泥は最下部に沈殿しているもので、たとえスカムがなく上澄みがきれいでも下には厚くたまっています。使用しているとスカムと汚泥の生成により槽内のスペースが狭くなってきて、浄化に必要な滞留時間が保たれないため、1年周期で抜き取ることが必要です。 |
|
放流管渠(かんきょ) |
流入管渠の項を参照ください。 |
|
槽内水位 |
浄化槽はひとつの装置です。どこかに詰まりや亀裂、破損があると水位上昇や低下の原因となり、機能低下を招きます。 |
|
生物活動 |
浄化槽内に住む、生物の状況をSV,水温、透視度等から総合的に判断します。 |
|
酸化室状況* |
平面酸化板を使用している浄化槽の場合のみの項目です。生物膜が厚くなりすぎた場合は、少し洗い流してやり、適正な量に戻してやるというということです。この項目の「洗浄」とは、この作業を行ったことを指します。 |
|
通気 |
通気装置の開口部が塞がれていないか点検します。浄化槽保守点検記録票右部の「点検結果、管理者への連絡事項」欄もご覧ください。 |
|
衛生害虫発生 |
いわゆるハエや蚊の発生を内部目視で確認します。内部が暖かすぎたり、微生物が多い状況だったりすると発生も多く見られます。4月の初めから夏場にかけて殺虫シートを取り付けると有効です。 |
|
異物の混入 |
浄化槽内に、下着類や衛生用品、オムツ等が混入すると、詰まり、においの元となります。保守点検においては、それらを取り除き、予防措置を行っております。「管理者への連絡」欄もご覧ください。 |
|
バッキ攪拌状態* |
バッキとは、ブロワー(送風機)により、浄化槽内部に空気が送り込まれていることをいいます。空気がろ材にまんべんなく行き渡っているか、適量かどうか、点検します。 |
|
ろ材の目づまり* |
浄化槽によっては、ろ材(空気と微生物を接触させるための板状のもの)があります。そこに微生物が繁殖しすぎると目詰まりを起こし、却って空気と触れる部分が少なくなり、十分な機能が保てません。逆洗とは、通常の水流が起こる方向と逆方向から空気を送り、洗浄することで、付着した微生物をはがし、膜の目詰まりをはがすことで機能を正常化させる、ということです。 |
|
散気管 |
浄化槽に空気を送り込む一連の装置です。水槽に空気を入れるための、ボール状のブクブクと同じ効果が得られます。送り込む空気量を調節、適正量を保つようにします。 |
|
汚泥移送装置* |
第1室以降で発生した底部にたまっている汚泥を第1室に返送します。これは、汚泥の流出を防ぎ、第1室の浄化に必要な汚泥量を維持するためです。 |
|
流量調整装置* |
大量に一気に入ってきた汚水を沈殿分離室で流入調整しています。浄化槽内に、一気に汚水が水が流れ込むと、処理機能が追い付かず、未処理水が発生する恐れがあります。 |
|
沈殿室スカム返送* |
浮上した活性汚泥をばっ気室に返送します。これは、沈殿室からスカムが流出するのを防ぐためです。 |
|
放流水異常臭 |
管理士自身の鼻で、臭気から浄化槽の問題箇所をみつけます。 |
|
排水状況 |
浄化槽の最後の処理室から処理水を放流する排水管の様子を点検します。正常な水位を保っていることを確認し、地盤沈下や地震等の外因によって管が割れたり、詰まったりしていないかの目安となります。 |
付属機器点検
|
点検項目 |
説明 |
|
ブロア* |
風量が十分か、経年変化で寿命が近いのか、音でわかります。お客さまからも「音が大きくなった」「音がしなくなった」「今までとなんだか違う音がする」等連絡をいただきます。空気が送り込まれないと臭気が必ず発生します。はやめの対応をお勧めしています。 |
|
エアフィルター* |
ブロアの外気吸い込み口に、埃や異物をいっしょに吸い込まないようにフィルターを挟んでいます。点検時は毎回交換し、吸い込み口はブラシではらっています。ここのフィルターを掃除すると中の駆動部の負担が減るので、故障も減り長持ちします。 |
|
排水ポンプ* |
放流先が放流管より上に位置している場合、ポンプで強制的に汲み上げて放流しなければなりません。 |
|
消毒剤 |
処理水を放流前に消毒するための薬剤です。常時水に触れている状態を保つよう薬筒の設置状況を点検し、次の保守点検(大体3ヶ月後です)までに十分持続するような量を補給します。投入した場合はその下の欄に個数を記入しています。XML、XBL、XLとあるのは、薬剤の名前です。 |
-->